2023.09.16
ホスピタリティコラム
日本のホスピタリティが世界一と言われる4つの理由 ~日本のおもてなし文化のルーツとは?~
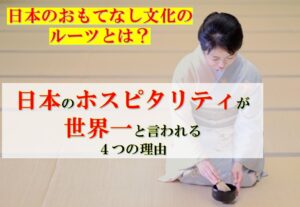
「日本のホスピタリティは世界一」と言われていますが、何故なのでしょうか?
それは、日本特有の「おもてなし文化」と深く関係があると考えられます。
東京オリンピックの誘致の際も日本の強みである「お・も・て・な・し」をアピールして、誘致に成功をいたしました。
また、東京ディズニーランドは世界一ホスピタリティレベルの高いディズニーランドだと言われており、
海外でサッカーのスタジアムで試合が終わった後にゴミを拾う日本人サポーターの姿が注目されたり、
震災などで被災されている皆さまが、物資などを配給される際に、順番を守り整列されている姿は、
日本人としては当たり前だと思っていますが、外国人にとっては理解できないようです。
このように、日本はおもてなしをはじめとする、
相手を「思いやり」「気遣い」「もてなす」文化が根付いており、
それが、世界一のホスピタリティである由縁です。
それでは、何故、このような日本特有のおもてなし文化が出来上がったのでしょうか?
これに関しては、様々な要因が複合的に絡み合って出来上がった文化だと考えており、
その主たる要因として考えられる4つを解説させていただきます。
1.村文化
まず、はじめに考えられるのは「村文化」の影響です。
日本人は集団で農作物や漁業、狩猟をして、それによって得られた「めぐみ」を、
皆で分け合って生活をしてきた成り立ちがあります。
従って、村民同士の協力が重視されていたと考えられ、
「村八分」という言葉が示すように、集団活動に対して逸脱した行動をする者は、
仲間外れにされるといった、村内の「社会性」が重視されていました。
そのような環境の中で、相手の感情を読み取る力や、他者とうまく付き合っていく協調性を養い、
ホスピタリティ力が高まったと考えられます。
2.神道と仏教の影響
私たちの中で一般的に信仰されている「神道」と「仏教」も日本のホスピタリティと大きく関係していると
考えられます。
まず、日本人はお盆にはお寺に行き先祖を自宅に迎え、正月には神社に行き初詣で願いごとを祈願をする。
このように、仏教も神道も両方受け入れる国民性があります。
また、お寺に行っても敷地内に他宗教の神社があることも珍しくありません。
このように信仰に対して柔軟であることも、外国のような宗教観での争いなどがなく、
お互いを尊重する文化が醸成されている要因として考えられます。
また、神道は私たちの身近にある、山、川、森、滝などへの深い敬意を持ち、
それらに神が宿り、私たちを見守ってくれていると考えられています。
従って信仰において、神々への感謝が大切な価値観となっていることもホスピタリティに考え方に繋がっています。
また神社特有の「お祭り」の時の祝宴でも、参拝者や訪問者に対するもてなしが成され、
ゲストを厚遇して喜ばせる文化が根付いた要因と考えられます。
このように神道は日本人のアイデンティティに深く結びついており、神道の価値観や儀礼は、
日本のもてなし文化に深く関係していると考えられます。
一方で仏教に関しても、善意と思いやりを重要な価値観としており、心の浄化と内面の平和を追求する宗教です。
この点においても日本人が内面的に安定し、他者に対して優しさや寛容であるということが、
世界一のホスピタリティに繋がっていると考えられます。
このように多神教、神道、仏教といった日本人の宗教観も世界一のホスピタリティに、
大きな影響を与えたことは間違いないでしょう。
3.和を大切にする
「日本人の心」=「和の心」といっても過言ではありません。
何故ならば、「和」は日本を言い表している言葉だからです。
「和食」・・・日本の食事
「和紙」・・・日本の紙
「和訳」・・・日本語に訳す
このように「和」は「日本」そのものを指しています。
また、年号においても「令和」「昭和」といったように「和」という字が使われているように、
日本にとって「和」は大切な意味を持ちます。
それでは、「和」という言葉はどのような意味があるのでしょうか?
「和」を辞書で調べると、
「和とは、仲よくすること。互いに相手を大切にし、協力し合う関係にあること。」
とあります。
聖徳太子が制定したという17条憲法の第一条に「和をもって貴しとなす」という条文があります。
故事ことわざ辞典によれば「何事をやるにも、みんなが仲良くやり、いさかいを起こさない のが良いということ」
とあります。
ちなみに、この「和をもって貴しとなす」は「~をもって~となす」から「もてなす」の語源という説もあり、
「おもてなし」の考え方と深い関連があると考えられています。
このように、「和」は日本人の心の中で調和、協力、共感、対立の回避、自然との調和など、
さまざまな要素と関連づけられており、日本文化と日本人の価値観に深く根ざしています。
この「和の心」が、日本人の「もてなし」に対する行動や考え方に大きな影響を与えていると考えられます。
4.礼儀を重んじる
そして、最後が日本人は礼儀を重んじるという点です。
そもそも日本人は、「茶道」「華道」「書道」といった「道」を大切にする文化があります。
この道というのは、所作や動作を「道」として極めることにより、
身体と精神の訓練を通じて成長や精神的な洗練を追求する日本特有の文化です。
そして、その道を追求する上で、相手に対する道義や礼儀、作法を重んじることを大切にしています。
このことからも相手を尊重し、リスペクトするということもホスピタリティの価値観と共通しています。
そして、このもてなし文化を語る上で、茶道を広めた千利休を外すことはできません。
茶道は、もてなしの精神を体現する一つの方法として位置付けられており、
ゲストに茶を振る舞い、もてなす機会を提供する中で、
「茶室のしつらえ」「茶碗」「和菓子」など、その場を「一期一会」の機会として考えて、
ゲストの事を心から想い、気遣い、もてなすことを大切にしています。
このように茶道は、日本文化に深いつながりを持ち、日本人の価値観や精神に大きな影響を与えています。
そして茶道は、もてなしの文化を通じて人々を結びつけ、ゲストを大切にし、心から歓迎する、
日本の伝統的なアプローチを象徴しています。
ホスピタリティ経営・コンサルティング・セミナー・講演のことなら
ザ・ホスピタリティーチーム
CATEGORY
NEW ENTRY
RELATED POST関連記事表示
TOPICSトピックス
マネジメントコラム
2024.07.19
失敗しない!サービス業向け研修会社の選び方 ~ ザ・ホスピタリティチームと他研修会社の違い ~
ザ・ホスピタリティチームでは、サービス業に特化したソリューションを研修やコンサルティングのサービ...
マネジメントコラム
2024.07.14
職場の社員同士の「関係の質」を高める方法 ~組織の循環モデルから学ぶ組織を成功に導く方法~
1.組織の成功循環モデルとは? 最近注目されている組織論で、マサチューセッツ工...
ホスピタリティコラム
2024.07.05
サービス業におけるカスタマーハラスメント対策とは?
最近話題に挙がるカスタマーハラスメント、そのカスタマーハラスメント対策は、 企業の健全な運営と...













